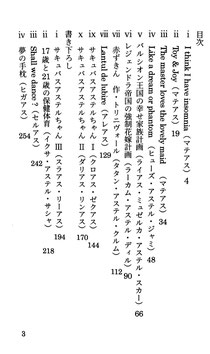
サキュバスⅢ
スラッシュ×アステル
淫語/Dキス/正常位/手コキ/フェラ/騎乗位
幼なじみのテントの隙間からは明かりが漏れ、食欲をそそる甘い香りが漂う。私は空腹を訴えるお腹を宥めつつ入口の布を捲った。
「スラッシュ、まだ起きてる…?」
「お、お前! こんな時間に何しに来たんだよ…って、何だよその格好は! まさかそれでウロウロしてたんじゃねえよな⁉ 他の野郎に見られたらどうすんだよ⁉」
ベッドに腰掛けていたスラッシュは私の元に駆け寄ると、焦った表情で問い詰める。ガクガクと前後に身体を揺すられ、肩に指が食い込んだ。
「い、痛いよスラッシュ……」
「あ、わ、悪ぃ…だけどマジで何があったんだよ。そんな格好で男の部屋に入って…勘違いするだろうが……」
「えっ? ごめん、よく聞こえなかった……」
「…何でもねえよ」
「くんくん…スラッシュ…もしかして今オナニーしてた?」
「は……?」
甘い匂いを辿りベッド脇のゴミ箱の中を覗くと、予想通り丸められたティッシュが一番上に乗っている。
「ばっ、バカ! やめろ! 見んな!」
「やっぱり…しかもこのティッシュの量…一回じゃないよね……」
「別に良いだろ…! つか、見んな!」
「よくないよ…勿体ない……」
スラッシュをジトリと横目で見ながら、一つ摘まんで口の中に放り込む。もぐもぐと咀嚼するとジワリと染み出した精液が唾液と混ざり合う。スラッシュは一瞬固まった後、真っ赤になって私を止めた。
「は……? お前、何して…バカ! 吐き出せって!」
「だって…スラッシュが出しちゃうから…私、精液を食べないと生きていけない身体になっちゃったの……」
「は……?」
「もうっ、さっきからそればっかり」
「いやいや、仕方ねえだろ…ダメだ…全然わかんねえ……」
「でもオナニーしちゃったなら、もう精液出ないよね? じゃあ、帰る」
「ま、待てって! 帰ってどうすんだよ…まさか他の野郎の部屋に行くんじゃないだろうな?」
「そうだけど……」
「マジかよ…おい、こっち来い」
二人並んでベッドに腰掛けると、スラッシュは混乱した表情で切り出す。
「……先生には相談したか?」
「してないよ」
「今日はもう寝てそうだし、明日先生に相談しに行こうぜ。何があったか知らねえけど、お前だってそんな状態イヤだろ?」
「…………」
「はぁ…そんな不満そうな顔すんじゃねえよ」
スラッシュはそう言うとぎゅっと私を抱き締めた。身体も、首筋にかかる吐息も燃えるように熱く、ドクドクと大きな鼓動が触れる肌越しに伝わってくる。
「…恥ずかしがったり、嫌がったりしねえんだな」
「うん。だって私スラッシュのこと好きだし」
「そんな簡単に…言うんじゃねえよ……」
「んっ……」
押し付けられるように唇が合わさり、そのままベッドの上に倒される。天井のランプの光がキラキラ眩しくて思わず目を細めた。
「俺がどんだけお前のこと好きだと思ってんだよ……」
「そんなの、わかんないよ…スラッシュは私のこと女らしくないとか、そんなんじゃ嫁にいけないとか言ってたから、異性として見てないんだと思ってた」
「バカ…俺はお前しか女として見てねえっつの……」
再びスラッシュの顔が近付き、角度を変えては何度もキスを繰り返す。豆のたくさんある手の平が私の脚を確かめるようにぎこちなく這った。
「あっ…スラッシュ……」
「んっ…はあっ…ずっとお前だけを見てきて…今さら他の奴を好きになんかなれねえよ…つか、どうやって好きになるかなんて忘れた……」
スラッシュは私の胸元を下げると、零れた乳房にかぶりつきもう片方も形が変わるほど揉む。急な刺激に嬌声を上げたのも束の間、私の下半身を覆う布も手荒く剥ぎ取られ、彼の指がグチュリと音を立てて奥へと侵入してきた。
リーンハルト×アステル
淫語/Dキス/レイプ風味/手マン/クリ責め/正常位/騎乗位
物音一つ立てず暗い部屋の中に入った直後、ベッドの黒い影が起き上がる。
「……姫? こんな時間に男の部屋に来てはいけないよ。もし添い寝が欲しいなら、俺が君の部屋へ喜んで行くさ」
「ウフフ♡オヒメサマの部屋にそのアブナイものも持ってくるつもりかしら~? ケハイをケしても気付くなんて、さすが騎士団長サマね♡もしかしてワタシのこともごゾンじ?」
「…最近グランロットで娼婦が行方不明になり、数日後に衰弱した状態で発見される事件が相次いで報告されている。彼女達は全員記憶が無く、魔物の仕業ではないかと疑っていたところだ」
「セーカイ♡ワタシってすぐおナカがすくから困っちゃって♡タダでヤリたい男なんてそこら中にコロがってるけど、女のカラダがもたないのよね~その点このコはジョーブでイイカンジ♡」
「ふざけるなっ…! 今すぐ姫の身体から出て行け…!」
「キャ~♡コワ~イ♡イケメンがスゴむとハクリョクあるわね♡でも…ジョーキョーわかってるのかしら? ワタシはこのコを殺せるのよ♡」
「……それも魔王の命令かい?」
「チガウわ♡ワタシ人間にホロんでホしくないのよね~ゴハンなくなっちゃうし♡」
「なら何が望みかな? 姫の身体から出て行って貰うにはどうしたら良い?」
「そうね~アナタずいぶんアソんでるみたいじゃない♡ワタシをイかせられたら、このコから出ていってあげるワ♡」
「ふふ、そんなことで良いのかい? ずいぶん可愛らしいお願いだね」
「ウフフ♡コッチもアナタがホンキになるようにするケドね♡」
「それはどういう……」
目を開くと、眉間に皺が寄り戸惑った顔のリーンハルトさんが視界に飛び込んでくる。
「ん…リーンハルト、さん? えっ? ベッド? ここは一体……」
「…姫⁉ もしかして…戻ったのかい? いや、ツノや羽はそのまま……」
「えっと…私、自分の部屋のベッドで寝ていたと思うんですけど…これはどういう状況ですか…?」
「…………」
「リーンハルトさん?」
「それはね…こういうことをする状況だよ……」
リーンハルトさんの顔が近付き、口を塞がれる。熱い舌で唇をこじ開けられ、舌を絡め取られる。舌先を吸われ、翻弄するような動きに息が上がった。
「んっ…あっ…リーンハルトさん…なんで…いきなり…こんな……」
「大丈夫だよ…俺に任せて。姫は俺の腕の中で可愛く囀ってくれれば良いよ」
「ま、待って下さい…!私たち、恋人でもないですし、ダメだと思います…!」
「じゃあ、姫は俺の恋人になってくれる? 俺は出逢ってから毎日姫に好意を伝え続けているんだけどな」
「それは…私だけじゃなくて他の女性にも言ってますし……」
「ふふっ、嫉妬しているのかい? 可愛いね。こうやって俺が本気の愛を囁くのは君だけだよ…姫……」
「でも、やっぱり何かおかしいです…今のリーンハルトさんは、いつもと様子が違う気がします……」
「いつもと違うのは君の方だろう? 今夜の姫は男を誘う瞳をしているじゃないか」
反論をする前に再び口を塞がれる。さらに濃厚さを増すキスに酔ったように頭の中が揺れていく。
「んっ…姫はキスが上手だね…たくさん練習したのかな?」
「はあ…はあ…そんな…私、初めてです……」
「嘘は良くないよ…ほらここ、首筋に赤い痕が付いてる。一体誰のものかな?」
「えっ…本当ですか⁉ なんで…⁉」
「君の普段着で隠せない場所に付けるなんて、よほど独占欲が強い男なんだろうね…俺も人のことは言えないけど」
リーンハルトさんが指でなぞっていたその場所に唇を寄せると、熱い痺れが走る。
「痛っ…!」
「っ、はあ…他の男が口付けたと思うと反吐が出そうだ…けど、これで上書きされたね。ねえ姫、次はどこに痕を残して欲しい?」
「そんな、やめて下さい! リーンハルトさん、一体どうしたんですか…あっ…!」
私の抵抗も空しく、肩に、鎖骨に、脇腹に、内腿に…全身に赤が点々と肌に焼きついていく。リーンハルトさんはそれを見て私の爪先に口付けながら満足そうな笑みを浮かべた。
「ああ…とても綺麗だよ。まるで赤いバラの花びらが散っているみたいだね……」
「いやっ…あっ…や、やめて下さい…リーンハルトさん、なんでこんな酷いこと……」
「酷い? 君の方が酷いことをしてるんじゃないかな? 男心を弄んできたんだろう? 今だって散々俺のことを焦らして…煽ってるじゃないか」
「そんな、煽ってません! よく分かりませんが…何か…誤解されているんですか…?」
「誤解、ね……それなら姫も俺のことを誤解しているよ。俺はこういう酷いことも平気でする男さ」
リーンハルトさんは強引に私の衣を剥ぎ取ると、硬く尖る乳首に歯を立てる。痛みに小さな悲鳴が漏れるが、彼は逃げようとする身体を抑えつけ、膣内に指をグチュリと突き立てた。
[newpage]
17歳と21歳の保健体育
イクサ・アステル・サシャ
3P/学パロ/Dキス/クリ責め/クンニ/乳首責め/Gスポ/正常位/対面座位/ポルチオ/連続絶頂
ここはオトメ学園高等部二年二組の教室。ほとんどの生徒が下校するか部活動に勤しむ放課後、教室には私と、不機嫌なオーラを全身から発するクラスメートのイクサさん、それから教壇に立つサシャ先生がいた。先生はいつも通りのほほんとした口調で話し始める。
「イクサくんは保健のテストが0点でしたねー」
「…勉強する意味が分からないからな」
「アステルさんは点数はそこまで悪くなかったですが、性に関するところだけ全部空欄でしたねー」
「ご、ごめんなさい」
「はい、ということで、お二人は居残り補習ですー」
「…下らない。帰って寝る」
「だめですよー。ちゃんと受けないとアステルさんやスラッシュくんの後輩になっちゃいますよー?」
イクサさんは苦々しい顔をすると浮かせた腰を戻した。この間の期末テストで特に問題があると判断された私たちは、この特別補習を受けなければ進級が出来ないらしい。
「…早く終わらせろ。というか、保健体育の教師はリーンハルトだろう。なんで国語のお前がいるんだ」
「今日リーンハルトは保護者会に出席しなければならなかったので、その代わりですー。彼が出ると寄付の集まり具合がだいぶ違いますからー」
「リーンハルト先生、流石です……」
「あいつは教師じゃなくてホストの方が向いてるんじゃないか? 大体、お前に保健体育が教えられるとは思えない」
「むー、馬鹿にしないでくださいー。ちゃんと知識はありますよー」
「イクサさん…ちょっと落ち着きませんか? 早く補習が終わればその分早く帰れると思います」
イクサさんは相当気が立っているようで、いつもより挑発するような言動を取っている。私が宥めるとイクサさんはチラリと見て溜息を吐いた。
「はぁ…早くしろ」
「はーい。じゃあテスト問題の復習をしましょうねー。第一問、『ディープキスの方法とその効果を答えなさい』」
「頭が痛い…なあ、問題がおかしくないか?」
「リーンハルトの教育方針は『実用的・実践的』らしいですー。アステルさん、答えられますかー?」
「はい。ええっと…確か、軽いキスを何度か繰り返した後に、お互いの…舌をか、からめて…その……」
恥ずかしくて真っ赤になってしまうと、サシャ先生は焦ったように遮る。
「わわっ、すみませんー…口に出すのは恥ずかしいですよねー」
「ごめんなさい……」
「そもそも唇を合わせて何になるんだ? 意味が分からないな」
「えーっと恋人同士だと興奮が高まったり、愛情が深まるらしいですー。僕も経験が無いので分かりませんが……」
「お前も人に偉そうに言える立場じゃないってことか」
三人の間に重い沈黙が流れる。サシャ先生は落ち込んでいるし、このままではイクサさんの機嫌がますます悪くなってしまう。
「あ、あの…実際に…してみますか?」
「は?」
「あー! それはいい考えですねー」
「お前…何を言い出すかと思えば…さっきまで恥ずかしがってたくせに、どういう風の吹き回しだ」
「も、もちろん恥ずかしいですし、本当にはしませんけど…その、イクサさんはする意味が分からないと言ってたので、フリだけでもしてみたらどうかなって……」
「呆れた。そんなバカらしいこと出来るわけ……」
「じゃあアステルさん、僕とキスしてもらえますかー?」
「…………は?」
「わかりました」
立ち上がり、サシャ先生の体温を感じる位に近付く。少し上にあるブラウンの瞳を見つめると鼓動が早くなり、微かに漂う紙とお茶の香りがそれを加速させた。
「ええっと、背中、失礼しますねー。あなたも僕の背中に手を回してみて下さいー」
「わ、わかりました」
「あなたの手、あったかいですね…ふふっ、なんだかドキドキしてきましたー。もう少し顔を近付けても良いですかー?」
「はい。大丈夫です…でもサシャ先生の眼鏡が当たってしまうかも……」
「確かにそうですねー。じゃあ眼鏡は外して、机の上に置いておきましょうー」
「なんだこれは。地獄か? 俺は一体何を見させられているんだ」
イクサさんの呆れ声も聞こえていないかのように、サシャ先生は眼鏡を外すと私の肩を引き寄せ、顔を覗き込んだ。
「はー、近くで見るあなたも可愛いですねー」
「おい、サシャ、コイツと顔が近いぞ。離れろ」
「すみませんー、眼鏡が無いとよく見えませんのでー。ふむふむ…ほっぺが真っ赤で可愛いですねー。瞳もいつもより潤んでいるような…わわっ!」
「んっ…!」
ギリギリまで顔を寄せたサシャ先生がバランスを崩す。サシャ先生の顔が近付きギュッと目を瞑ったその瞬間、唇に温かいものが触れる。何が起きたのか分からず、固まった私の身体はサシャ先生から引き剥がされ、イクサさんの胸の中に収まっていた。
「おい…! 何コイツと本当にキスしてるんだ。教育委員会に訴えるぞ!」
「す、すみませんー」
「お前、こっち向け」
「い、イクサさん…?」
「コイツとキスしたのに俺としないのは不公平だろうが」
「ええっ…! んっ……」
強引に唇が合わさり、薄い舌が入り込んで私の舌と触れる。二人でぎこちなく舌を絡み合わせると、腔内には唾液が溢れ、頭がぼーっとしていった。
「はあっ…はっ……」
「あっ…イクサさん…んっ……」
「あー、ずるいですー。僕はディープキスしていませんー」
サシャ先生の不満そうな声に唇は解放されたが、イクサさんは私の身体をギュッと抱きしめたままサシャ先生を睨みつける。
「…知るか。しなかったお前が悪い」
「むー、アステルさん、僕とももう一度キスしてくれますかー?」
「えっ…は、はい……」
「おい、そしたら俺が一回なのにサシャは二回キスすることになるだろうが…!」
「じゃあ僕の後にイクサくんがもう一度キスをすれば……」
「あ、あの…! 補習の続きをした方が良いと思います!」
「あー、そうでしたー。えーと、第二問『女性の主な性感帯を三つあげ、その愛撫の仕方を答えなさい』はー、これは難問ですねー」
[newpage]
Shall we dance?
セルピコ×アステル
立ちバック/淫語/言葉責め
セルピコさんがグランスレイヤーになった褒美として望んだのは、グランロット城のダンスホールの貸切だった。私は彼の選んだ慣れない豪奢なドレスを着て、耳も首もキラキラと光っている。
広間の扉をそっと開くと、長い髪を一つに纏め、私のドレスと同じ色のフォーマルな服に身を包むセルピコさんがぼんやりと佇んでいた。人形のように整った横顔は別人のようで声を掛けるのを躊躇ってしまうが、彼は私に気付くと一瞬で花のような笑顔を見せる。
「アステルちゃん! あはっ、すっごく可愛いね! やっぱり二人きりにして正解だった! 君のこんな姿…誰にも見せたくないもん☆」
そう言ってセルピコさんは私をギュッと抱きしめる。いつもとは違う香水を付けているのだろうか、大人っぽい香りに包まれ胸が高鳴る。この広い広いホールには私とセルピコさんの二人きり。それも、セルピコさんの願いだった。
「セルピコさんも凄く似合ってます。本物の王子様みたいです」
「ありがとー☆ 君も本物のお姫さまみたい…ううん、本物のお姫さまよりもキレイだよ」
「…ありがとうございます」
にっこりと微笑む彼に頬が熱くなる。最近のセルピコさんは時々こういう風に笑い、どちらが年上なのか分からなくなってしまう。返す褒め言葉が上手く見つからないでいると、彼はレコードの方に歩いて行きながらぽつりぽつりと話し始めた。
「僕ね、子供の頃すっごく好きな絵本があって…女の子が魔法でお姫様になって、お城の舞踏会で王子様と一緒に踊るんだ。眠れない夜はそのシーンを何度も何度も読んでた……」
彼がくるくると回るレコードに針を落とすと、柔らかな旋律が流れる。こちらへ振り向いた王子様は、おもむろに跪きそっと私の手を取った。
「プリンセス、僕と踊っていただけませんか?」
いつもより低く、でも透き通る声がホールに響く。エメラルドのような瞳に射抜かれ、一瞬、時が止まった。
「…はい」
「あはっ、一回やってみたかったんだよねー! 今のどう? ドキドキした?」
「すごくドキドキしました……」
「やったー! 大成功☆」
セルピコさんは無邪気に跳ねると、流れるようにチュッと私のほっぺに軽くキスをした。彼はそのまま固まる私の耳元で甘く囁く。
「キミをいっぱいドキドキさせて…もっともーっと僕のこと好きになってもらうんだから…覚悟してね?」
「セルピコさん……」
「照れちゃってかわいー! もー、あんまり可愛い顔しちゃダーメ! 僕だけが君のこと好きになっちゃうでしょー?」
「わ、私もセルピコさんのこと、負けないくらい好きですから……」
「だーかーらー! そーやって可愛いこと言うのも禁止! それとも…僕のこと誘ってる?」
上目遣いで首を傾げ、妖しく笑う彼の方が誘っていると思うけれど、その言葉は飲み込んだ。これ以上は心臓が持たないし、どうやったって彼には敵わない。
「なんてね? さ、早く踊ろうよ!」
「でも私、ダンスはあまり上手じゃなくて……」
「だいじょーぶだよ! 僕がリードするから!いくよー、いち、にー、さん!」
手を引き軽やかに足を運ぶセルピコさんに、たどたどしいステップでついていく。なんとか足元を見ないように慎重に踊るが、足裏に柔らかさを感じ思わず身体を引いた。
「きゃっ! ご、ごめんなさい」
しかし、繋がれた手と腰に回された腕に引き寄せられて、二つの身体はさらに密着していた。
「離れちゃダメだよ。世界一のスターを信じて…もっと近付いて。足元じゃなくて僕の目を見てね…いち、に、さん、いち、に、さん……」
どんどん顔が近付き、今にもキスしそうな距離に、熱が上り何も考えられなくなる。それなのに視線を外せない。
[newpage]
夢の手枕
ヒガン×アステル
Dキス/クンニ/素股/正常位/間接的な破瓜表現/暗め
――随分長く夢を見ていたような気がする
「おはようさん…まだ眠いかのう」
徐々に霞がかった視界が晴れていくと、板目の天井を背に微笑むヒガンさんが現れる。私は胡座をかいた彼の膝の上に頭を乗せ、仰向けに寝ているらしい。
「ヒガンさん…?」
「そうじゃよ。身体はどうじゃ? 辛くないか?」
「少し頭が重くて…ここはどこですか? 私、今まで何をしていたんでしょう…?」
何か、忘れてるような
「ここか? ここはわしの城じゃ」
「お城…? ヒガンさん、商人じゃなかったんですか?」
「にゃはっ、ある時は敏腕商人、またある時は可憐な勇者さんを守るスレイヤー、その正体はイヅルノの王じゃ…! 隠しとってすまんの」
「ふふっ…そうだったんですね。でも、なんだか分かる気がします。ヒガンさんならきっといい王様だと思います…よいしょ」
上半身を起こすとクラリと頭が揺れる。ぼんやりと周りを見るととても広い座敷で、窓の外は夜空が広がっていた。若干の動き辛さから、服が変わっていることに気付く。
「あれ? この着物は……」
「わしがあんたのために選んだ着物じゃ…思った通りあんたの白い肌には赤が映えるわ。よお似合っとる」
そう言ったヒガンさんに背中から抱き締められる。首筋に熱い息がかかり、思わず身体を強張らせた。
「ひ、ヒガンさん…?」
「あんたは本当にええ香りがするのう……」
うなじに何度か口付けられた後、吸い付かれ、ピリッとした痺れが走る。
「きゃっ…!」
「可愛い声じゃな…もっと聞かせてくれんか」
着物の袷から手を差し込まれ、慣れた手つきで帯が解かれていく。私は肌が露わになる前に慌ててヒガンさんの手を掴んだ。
「ま、待ってくださいヒガンさん…! ダメです…そんないきなり…!」
「いきなりじゃなかろう…もう何度も肌を交わしておるのに、あんたはいつまでたっても初心で可愛いのう」
「えっ…私とヒガンさんは恋人、でしたか…?」
「いんや、違う……」
手首を掴まれ、私は畳に押し倒されていた。ヒガンさんの顔に影が落ち、表情があまり見えない。
「わしとあんたは結婚したんじゃ…魔王を倒して、世界は平和になって…あんたは勇者から一人のおなごに戻ったんじゃ……」
頭の中を白く濃い霧が覆う。彼の言葉が一つとして、自分の中で符合しない。
「ごめんなさい…私、覚えてません…世界を救う為に皆さんと旅をして戦って…それから……」
それから?
暗闇の中をたどたどしく歩くように記憶を探っていると、深い口付けで現実に引き戻される。驚いて開いた口に熱い舌が入り込み、吐息を押し込まれた。
「んっ…ヒガン、さんっ……」
「アステルさん…無理に思い出そうとせんでいい…勇者の役目は大変だったからの…でももう終わったんじゃ……」
「はあ…はあ…そんな…ヒガンさんはそれでいいんですか?」
「ああ…過去は忘れても、これから二人で思い出を作ればええんじゃ。今はもう勇者じゃのうて、一人のおなご…あんたは自分の幸せだけ考えとくれ……」
「私の、幸せ……」
いつも私の隣に居たのは?
